孫福初代会長のメッセージ

大学行政管理学会 初代会長 孫福 弘
(1997年1月11日 於 慶応義塾大学三田キャンパス)
大学行政管理学会 発会式 孫福初代会長 ご挨拶
ただいまご紹介のありました慶應の孫福でございます。この大学行政管理学会の発会式の冒頭に当たりまして、発起人・世話人を代表いたしまして、ひと言ご挨拶を申し上げたいと思います。
本日はかくも大勢の方々にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。
実はこのホールの席数・定員が240席でございまして、正直申しますと今日のご出席のご返事をいただいております方々の数が実は250名を超えております。その意味で今はまだ多少席に余裕がございますけれども、遅れて来られる方々合わせて、立ち見の方がでないことをひたすら念じておる次第でございまして、大体こういう会の場合にご出席の返事をいただきましても、当日急にご都合が悪くなって欠席されるという方が何人かいらっしゃいますので、その数が適当な数出まして、皆さんお席について発会式をお迎えいただけることができることをひたすら念じておる次第でございます。
少し発会に至るまでの経緯についてもお話をしておく必要があるだろうと思いますけれども、まず私ども7人の世話人が昨年の夏から秋にかけまして何回か相集いまして、どんなかたちでこの会の発足に向けて準備をしていったらいいだろうかということで何回か検討いたしました。その結果、やはり全国各地の大学の方々の中から発起人をお願いして、その発起人の方々の名前を連ねさせていただいて、それで皆様方に呼びかけるのがいいのではないかということになりまして、発起人の方々を私どもの間で選ばせていただいて、ご無理をお願いして発起人になっていただいたという事情がございます。
そうしまして、昨年の11月11日だったと思いますけれども、全国の私立大学の団体の代表者の方々宛にご案内を差し上げました。これは代表の方宛に一通ずつお出しいたしまして、是非それぞれの貴学の管理職の方々に周知徹底をさせていただきたいということをお願いした次第でございます。
それから約一か月後の12月15日に一応の締め切りというものを設けさせていただいたということでございます。12月15日時点で既に私どもの予想を遙かに超えまして320名を超える数のお申込みをいただきました。その後も五月雨式に毎日私のところの人事のFAXは垂れ流し状態を続けておりまして、今日付けでのお申込みもございました。
それで最終の数字でございますけれども、お手元の資料の中で一枚ものの資料があると思います。その一枚ものの資料をご覧いただきますと、そこに地域ブロック別とか大学の加盟団体ごとに私立大学連盟加盟校、私学協会・私大協会加盟校というかたちで、加盟校別とかあるいは地域ブロックごとにわけた内訳が書いてございますが、とにかくトータルの数字で350校という数字が、実は1月9日付で一応締めた段階での入会申込の数でございます。
そういうことでございまして、これは実はそのような経緯を申しました中でもおわかりいただけると思いますが、とりあえず全国の私立大学、全大学にお出しをしたということでございますけれども、もちろん学会の名前からもおわかりのように「大学行政管理学会」という名前自体はなにもその対象を私立大学に限るというつもりは当初からございません。ただ呼びかけの仕方がなかなか難しいということで、国立大学それから公立大学については若干後回しになるというかたちで、私学でとにかく発足をしようと、こういうことを世話人の間でも話し合って、こういうかたちで発会をさせていただく、こういうことでございますので、今後の大きな課題のひとつとして国立・公立の管理職の方々にどういうかたちで呼びかけていくかということが、このあと理事会等も発足するわけでございますけれども、そこの理事会、あるいは新しい役員の新しい任務・課題の大きなテーマのひとつだと思っております。
そういうことで私どもは最初はとてもこんな大きな数が集まるとは思っておりませんで、せいぜい私どもの予測としては100人が単位と考えていまして、100人以下だとちょっと発足としては寂しいかなと。ただし150人を超えるような数になるとこれは最初から望めないだろうから、できるだけ最初はあまり無理をしないで小規模なかたちでスタートをさせていただいて、徐々に地道な活動をして力をつけていきながら、さらに会員を拡大していくということを考えようかなというような構想でございました。
その意味で、例えばこういう会の運営に当たりますと事務局などというのは大変な作業なわけですけれども、まあ100人、150人ぐらいなところであれば、なんとか我々の間で手弁当で、お互いに大学の回り持ち等でなんとかやっていけるんじゃないかと気楽に考えていたわけですね。ところが現在の段階で350校。おそらくこの調子で行きますと今年の末とか来年になりますと400とか500とかいう数をおそらく展望することになるだろうと思うんですね。そうなりますと、とても手弁当でやるということはできない。従いまして、おそらく事務局などの在り方というものも新しい役員の間でお考えをいただく必要がある非常に大きなテーマだと思っております。
そういうことでありまして、私ども世話人のほうとしては嬉しい悲鳴というところでございますけれども、これの原因を考えてみますと、ひとつは私どもがお願いしました発起人の方々に大変ご尽力をいただいて、ご勧誘をいただいたということもありまして、その意味で、今日ご出席の発起人の方々に私ども大変感謝をしておるわけでございますけれども、もう一つの要因はやはりひとつこの今の時代の要請ということがあるだろうと思うんですね。
新しい時代に於いては、大学の行政職員といいましょうか、管理職員、この人たちの戦力の強化といいましょうか、そういう点が時代として緊急な要請課題であろうと思うんですね。その意味で、大学のトップがそのことをいち早く察知をされて、大学の戦略として、こういう学会に期待をされて、是非そこに参加をするようにというかたちで、おそらくいろんなかたちの支援対策も含めて奨励をされておられる大学がいくつかあると私自身は漏れ聞いております。そういうことはたぶんあるだろうと思います。その意味で、我々この学会の運営をこれから担っていく皆さん方の中でも当然そういう方々が中心になっていただくわけですけれども、そういう方々の責任あるいは参加される皆様方の責任自体が非常に重いと思う次第でございます。
学会設立の趣旨というのはもう趣意書に書いてございまして、皆さんお読みいただきましたので特にあえて繰り返す必要はないと思いますけれども、大学改革が今盛んに行われておりまして、大学改革花盛りという感じもいたしますけれども、その中で各大学で教員の人たちの頑張りというか、そういうことがかなり目につくようになってきた。東大などの教養学部の改革等にしましても非常に先生たちの改革意欲が旺盛であるということがありますし、私学の改革についても同じようなことがあるだろうと思いますけれども、そういう改革が持続的に続いていくかどうかということになりますと、ここの段階ではやはり行政管理職員に人を得るというか、そこの戦力アップ、パワーアップというところが、おそらく持続する改革、あるいは持続的な発展の課題になる、鍵になるんだろうと思っているわけであります。
その意味で、この学会の発足がそういう意味で我々自身の、お互いの切磋琢磨を通じてそういうお互いの質を高めるというか、あるいは我々自身の職員の管理職としての意識の転換といいましょうか、そういう点で大いに貢献できれば学会としての役割が充分果たせるということになるのではないかと思っている次第でございます。
この学会自体は今ちょうどここで産声を上げたばかりの新しい存在でありますけれども、どうか皆様方には是非積極的に学会の活動にご参加をいただいて、この学会そのものの存在意義というものが5年、10年、20年後を見たときに、むしろ大学の発展のためには欠くことの出来ない存在になっていれば、ここに集まっている皆様方にとっても大変意義のあることだと思いますし、私ども世話人としても大変嬉しいなと思う次第でございます。
そういうことでお互いに学会を発展させるために、あるいは我々自身の切磋琢磨のためにお互いに協力をして頑張っていきたいと思いますので、どうかご活躍をいただきたいということを申し上げまして冒頭の私のご挨拶にさせていただきたいと思います。
今日はどうもありがとうございました。
寄稿
村上 義紀 氏
大学行政管理学会創設メンバー・初代副会長、元早稲田大学副総長・常任理事
1)5月13日
メールがきた。私市(武庫川女子大学)さんからだった。三谷広報委員長(南山大学)の意を受けて、創設20周年記念に寄稿をお願いできるか、というものだった。 そうだ。21年前の、今日だった。1996年の5月13日、月曜日の午後の、この日こそ、大学行政管理学会の命が宿った日だったからである。この日を私市さん、三谷さんが知っていたかどうかは知らないが、創設に係わったわたしには、あの日を思いだすメールだったから、うれしくもあり、驚きもしたのである。 それにしてもJUAMが、よく、20年も続いてくれたものだ。育ててくださった歴代の会員の皆さまに、感謝の気持ちでいっぱいになる。
2)創設前史については
なんどか話したり、書いたりしたが、若い会員も多くなっているので、今後の会運営の参考になれば、と今いちど記しておくことにしたい。 なにごともいまある組織というのは、だれかが提案し、創設に至る経緯がある。1996年(平成8)5月13日の月曜日の午後、私立大学連盟研修企画委員会が、市ヶ谷の私学会館別館にある連盟会議室で開催された。世紀末の1990年代は、大学の変革が問われていた時代だったから、連盟の今後の研修をどうするかを論議した。だが、これ以上、新規事業で連盟事務局の負担もかけ難かったので、結論をえぬまま散会した。
3)同時代を生きた3人
この時、私大連研修企画委員会の委員になっていなければ、JUAMは誕生していなかっただろう。慶應の孫福弘さんは人事部長、亜細亜の山本忠士さんは理事・総務部長、小生は早稲田の財務部長で翌月から総長室長に内定していた。みな部長職で、戦前の生まれだった。かつて3人は、来日してくる留学生問題を研究するJAFSAの名で知られる外国人留学生問題研究会(現在は「国際交流協議会」という)の会員だったから、お互いに知ってはいたが、ともに飲んだことはなかった。散会と同時に立ちあがりながら、顔を見合わせ、「いっぱいやろうか」となった。かくして私学会館2階のレストラン「フォッセ」に立寄った。初夏の汗ばむ夕べでビールがすすみ、「連盟からスピン・アウトして、連盟を超えた新しい研修を立ち上げるか」と話が弾み、3人はすぐに一致した。弾みとは恐ろしい。「学会を創るか」と孫の御兄さんがハレンチにも言う。山本の御兄さんも同調する。ハレンチを知る小生は、当初は研究会とするのがいいのではないか、と言っても多勢にはかてない。当時の大学教員にとっては、ジム職員ごときが、学会?って、笑わせるんじゃない、という雰囲気の時代だった。だから大学は運営するもので経営ということばもタブーだった頃である。結局、学会を創るということに同意したが、大学行政管理という名称にしたのは後のことである。
4)かくして、事務職員が大学行政・管理を研究する
学会を創ることを決め、その場で、次のことを申し合わせた。
① 学会という以上、私立大学連盟加盟校の枠を超えて全私立大学の職員を対象とすること
② 国立大学の職員への呼びかけは、学会運営の事務的力量から当初は呼びかけないこと
③ 会員の範囲を全私学の職員を対象とするかを論議したが、当初は運営に支障が生じないように、課長職以上の管理職者に絞って呼びかけることにしたこと
④ 学会が将来、保守化しないように、役員の任期は60歳までとし、かつ大学を退職したら正会員としない定めにして新陳代謝をはかること
⑤ 学会創設を発起した3人の世話人の他に、都内大学の共通の友人4人に呼びかけること
⑥ 世話人の準備に係わる費用は手弁当で取り組む了解をもらうこと
⑦ 学会の会員となった後の学会活動は自己負担を原則として呼びかけること、
の7つだった。
5)準備のための4人の世話人には
快く引き受けてもらった。第1回の世話人会の開催は7月1日(月)。以降、8月29日(木)、9月24日(火)と開催、学会のあり方を論議して、設立趣意書の原案作成は孫福さんにお願いすることになった。10月22日(火)、設立趣意書原案を検討。一読。世話人の意を汲んだなかなかの名文を起草してくれた。異論なく決定、すぐに印刷に発注した。そして11月1日(金)に、学長宛に趣意書封入作業(500通)をしながら、100名くらいの賛同者があればよしとするか、などの話しをしたことを思いだす。封入が会館の閉館時間までに間に合わず、残りの200通ぐらいは手分けして自宅に持ち帰り、投函することにした。その後、11月8日(金)、12月17日(火)と賛同者数を確認。そして新年を迎えた。世話人会最後の第8回目は1997年1月7日(月)、発会式の打ち合わせをした。かくして1月11日(土)14時半から慶應義塾大学での設立発会式に臨んだのであった。以上が学会創設前史の作業日誌である。
6)学会名称については
なんどか世話人会で議論し、大学管理学会、大学運営学会、あるいは大学経営学会はどうか、などが話題になった。大学管理ということばは、大学管理法(通称は「大管法」といった)という臨時の法律もあり、管理だけではイメージが強すぎる。では大学運営学会はどうか。大学の運営費がお国から交付される国立であればいざ知らず、私学では全く相いれない。では大学経営ではどうか。これもまた大方の私学では受け入れがたい。当時の大学はまだ経営ということばはタブーで、もうけ主義、マスプロ教育、学費値上げ、等々を連想させ、大学の組合からも批判されることが予想されたからだ。こうした論議を経て現在の大学行政管理学会という名称で、ゆるゆると船出をすることになった。
ただし、学会という名称はいかがなものか、といまでも暗に批判されることがある。いわゆる大学についての研究論文としては書きがたいためであろう。だが、論文ではなくても、いま大学が何をしているかについて史実、記録はしておくことはできる。
7)設立発起人を置く
さらに申し合わせたことがある。第2回目の世話人会だったと思うが、学会設立の呼びかけと設立後の運営には、全国を視野に入れた発起人が必要ではないかと。そこで北は北海道から南は九州・沖縄までを視野に入れて、なってほしい21人を決め、分担して電話をいれた。そのうち12人はわたしが関係した私立大学連盟職員総合研修の運営委員にお願いした。 1996年頃はまだe-mailのない時代だったから、電話に頼った。これが、会員資格を課長以上の管理職者に限定した理由のひとつでもあった。われわれ発起人となった3人も、世話人も本属校の本務があるから、学会発足後の運営破たんを恐れたからである。
学会会員の定年と役員の任期を定める件では、学会でこんな条件を付けるのはいかがなものか、という意見ももちろんあった。正論ではある。だが、これを決めておかないと、熱心さのあまり特定のひとが永く務めた結果、後継者の養成に支障がでる可能性をさけておきたいとの配慮からだった。
そして、手弁当の参加と運営を強調したのは、「職員が、学会って?」と言われてもおかしくない時代だったから、大学が理解して会費費用を大学が負担してくれるとはとても思えなかった。いま現在、理解が進んだかはわからないが、会員が1300名余を超えているところをみると、進んできたかな、とも思う。この手弁当の精神はいまも生きていると聞く。うれしい。なぜなら、手弁当であっても学びたいという心構えこそが長続きする秘訣だと考えていたからである。
会員資格は発足後ほどなく規約改正されて一般職員までに拡大された。手作業からインターネットの時代になったことが大きいだろう。2000年代にはいり、大学の外部環境が劇的に変化し、職員の仕事もまた変わらなければ対応できない時代になっている。その意味で、1997年の学会創設の効用はあったかもしれない。
8)3人が内々に申し合わせていたことがある
学会初代会長は孫福、初代副会長に村上、そして初代事務局長には山本が、いきがかり上最初の理事会で決定した。もとより事前に3人はこの役職に就く覚悟を決めていたことはいうまでもない。だが3人は、60歳も近くなっていたので、後継者となる4代目までの会長候補を予定して、その気になってもらうことにして運営した。
かくしてわれわれ3人は役職退任後、部会に出席することはあっても理事会には出ていないので、その後の活動方針には関与していない。私自身は創設メンバーということで退会後は名誉会員になったから、毎年の総会・研究集会には出席してきた。ただ、第9回の札幌のみは、前日には現地にいたが、私事で東京に帰った。2017年も出席すれば、19回出席したことになるが、その活動をともにできた。
9)総会・研究集会に思う
開催校が毎年変わってもその知恵は蓄積され、りっぱに運営されている。開催校と協力職員の働きがあってこそ、ではある。が、同時にその経験、その苦労は、大きな財産となったにちがいない。教員の学会開催を横目で見てきた職員も、いちどこの短期プロジェクトともいうべき体験をすれば、教育あるいは研究サーヴィスのあり方に思いを致す職員になれるだろう。将来は、小規模の大学であっても、連合で開催し、その経験を享受できる日があれば、と願っている。
ところで、大学職員の研究報告はなかなか難しい。成功事例であれば問題ないが、勤務する大学の問題提起となれば学外で発表するのは勇気がいる。そこでどこの大学の事例か特定できないように、複数の大学の研究事例としての報告となる。だがそれは迫力に欠ける。事例発表をしたいと思っても、学内事情は学外秘とされることが多い。学長や理事長等の大学の責任者であれば語りえようが、会員である職員がそうした報告をすれば、他校の者には興味津々で、おもしろいが、あとで聞き及んだ自己の大学からは批判される。したがって現状報告であっても消極的になるのではないかと思う。これは日本の私学が抱える大・中・小の規模の差、学部構成の差、場所の差、歴史の差などから私学の数だけ違いがあるから、共通の問題として浮かび上がらせることが難しいからではなかろうか。こういう現状のなかで、この学会会員が、どんな研究をし、発表するのか、は今後の課題であろう。
一つの分野に専門性のある人材育成も問われているが、特化した人材よりも、大学に関する幅広い教養をもったいわゆる総合型のアドミニストレイター人材養成がまだ必要だと思うこの頃である。私学の閉鎖性を打破、克服し、私学間での人事異動が当たり前にする研究も、わが学会の今後の課題として期待したいところである。
10)孫福賞創設のことども
孫福さんの逝去の報を聞いたのは、2004(平成16)年6月17日だった。JUAM創設年の1997年3月に、わたしが病に倒れて見舞ってくれた孫さんが、JUAM創設8年目に先に逝ってしまった。彼はわたしより5日だけ年下。大学こそ違え、同時代を生きた同士ともいうべき友だったから、その死に衝撃をうけた。斎場のある新横浜駅への車中、あることを考えていた。斎場に到着するや当時事務局長だった獨協大学の水野雄二さんにすぐに会い、彼の功績を顕彰する方法を理事会で考えてみてくれまいか、とお願いした。こうした思いはわたし一人の思いではなかったかも知れないが、原邦夫(慶應義塾大学)会長率いる理事会は直ちに検討され、今日の規約を定め、孫福賞を授与する運びになった。
彼は伊勢の出身であったからか、葬儀は6月20日神式で執り行われた。慶應義塾大学文学部で国文学を学び、学生時代は同人誌に小説を書いていたというから、書くことは手馴れていたようである。JUAM設立趣意書の起草文が素晴らしかったので、ほめたら、恥ずかしそうにそう言ったものである。彼との最初の出会いは、1965年であったと思うが、開設早々の八王子の大学セミナーハウスで開催された学生問題セミナーであった。孫福という名前が印象に残った。彼はその後、審査室、研究・教育情報センター、秘書課と約3年ごとに異動し、国際センターに12年余務めた。この時期はJAFSAの事務局長をしていたから、この間よくその件で国際業務を担当する早稲田の外事課にきていた。そして89年から藤沢の新学部(SFC)設置のために部長職になったが、通勤に不自由したのか自動車の運転免許証をとったと思う。1994年に人事部長に、96年には業務改善推進室長を兼務していたその時にJUAM創設の話をしている。その後、97年に塾監局長・理事を経て事務職から2001年総合政策学部教授に就任。04年3月に退職後、乞われて横浜市立大学の地方独立行政法人理事長含みで最高経営責任者に転じたが、途中で散った。 一方、JUAMの初代事務局長を担った山本さんについてもふれておかないわけにはいかない。
山本さんは、村上、孫福より1歳年下であったから、我々と全く同じ同時代を生きている。愛知県に生まれ、亜細亜大学商学部を卒業後、創立早々の香港中文大学新亜書院商学院経済学系を卒業しているから、中国語が堪能である。中華料理飯店に行くと中国語で料理を注文しなさいよと当方が言うものだから、彼の中国語の会話を耳にした。なかなかのものらしい。亜細亜大学では国際交流部長、学長室長、総務部長、理事に就任し、退職前には秘かに、JUAMの事務局長の仕事もしながら、日本大学通信制大学院総合社会情報研究科修士・博士課程を修了し、博士学位(総合社会文化)を得た。後に、2006年9月から中国・吉林省四平市吉林師範大学東亜研究所の外国人教員となって日本語を昨年まで教授した。なお、訪中前に、博士論文を一部修正して『近代中国の国恥記念日~日中間のコミニュケーション・ギャップの研究~』(A5判、386頁)と題する学術書を出版して、おどろいた。JUAM会員の博士号第一号であろう。
11)結びに大学職員の未来を考える
大学の現場から離れて16年にもなるから、最近の大学の動きには不案内だ。それだけではない。その変革の動きが在職中に比べると格段にはやくなっていると聞く。とくに若手の職員の業務量は増大し、多忙になっている。多くの業務が手作業から機械処理されたことから、データの作成も時間との競争になる。そして処理データからの情報を読み取る能力が必要になっている。近い将来は、いわゆる事務作業は機械が処理して判断までするかもしれない。将棋の電脳戦をみても最強のプロ棋士が勝てない。自動車も自動運転の時代が近いといわれる。そうなった時代になれば、判断業務さえも機械が即断、即決して処理してしまうかもしれない。そして事務処理は教員や学生自身がダイレクトに処理して、いままで中間に介在していた事務職員の仕事は不用になるかもしれない。いまでは当たり前になっている銀行預金の出し入れや予約や買い物さえもお客自身が作業をするではないか。大学の事務職が担ってきた業務のなかで、何が変化し、ひとが中間に介在しなくてもよいか、の研究をしておく必要がある。そうなればピラミッド組織の中間管理職は不用となり、機械で判断できない業務だけに対処するフロント人材が重視されて即決、処理するフラットな組織になるのではないだろうか。後方に座って稟議書にハンコを押す管理職は不用の時代がみえる。高度の判断力のあるフロントに配置できる相当数の人材、すなわちフロント・アドミニストレイターと少数のトップ・アドミニストレイターの養成が必要になるのではないか。また、ひとに直接接しない本部の仕事とされる予算、調達、決算等経理の業務と人事の給与計算業務は少人数でできる可能性が高い。職員の新しい仕事は、限りなく学生あるいは教員という不条理な人間に対する教育サーヴィスへとシフトしていくのではなかろうか。とくに学生への教育サーヴィスとは何かを研究し、それに対応できる人材の養成が、わが学会が取り組むべき大きな課題であろう。(2016年5月31日 記す)
山本 忠士 氏
吉林師範大学客座教授(元 亜細亜大学)、大学行政管理学会創設メンバー・初代事務局長
過日、創設20周年の大学行政管理学会総会に参加させていただいた。設立総会のあった慶應義塾大学が会場ということもあって、20年前のことが懐かしさとともによみがえってきた。当時、若々しかった方々が、今は組織の中枢で頑張っておられる姿に接することができて本当にうれしかった。
創設時のことは、村上義紀氏の「大学行政管理学会創設20周年に寄せて」に書かれているとおりであるので、ここではやや違った角度から学会設立当時のことに触れてみたい。記憶違いのこともあるかもしれないが、ご寛恕いただければ幸いである。
孫福さんの尽力
学会創設時の参加申し込み用紙には、住所、氏名、大学名、役職名、興味を持っている分野など通常の学会では考えられないほど記入項目が多かった。参加要件は課長職以上としていたこともやや風変りだった。なるべく多くの方々にご参加いただくというのが、この種の団体の常であるからだ。学会開設趣旨に「プロフェッショナルとしての大学行政管理職員の確立」とあるように、大学業務に対する経験を考慮したことがあった。しかし、どの程度の賛同が得られるか、全く予想もできなかった。管理運営体制、事務処理能力など何も整っておらず、まずは少人数でスタートできればスムーズに滑り出せるのではないか、との思いもあった。世話人・発起人は、皆それぞれに所属大学の枢要な立場にいて、日常業務を抱えていたから、最初からあまり過大なことを考えることなく、地道に自分たちの学会を育てたいとの思いが強かった。ただ、せっかく職員の学会ができるというのに、やる気のある若い人たちの道をふさぐように映り、失望された方もいたと聞いた。不快な思いをさせたことについてはお詫びする以外にない。とにかく、やってみる。あとは、反応を見ながら臨機応変に対応すればいいのではないか、ということである。
参加申し込み書類は、私立大学連盟の会議室をお借りし、世話人・発起人の有志で宛名書きと封入作業を行い、全国の私立大学に送られた。100名くらいの参加申し込みがあったら嬉しいね、などと話し合っていた。結果は、三百数十名という予想を超える方々から申し込みをいただいた。この時、すべての会員情報をEXCELに入力されたのは、孫福弘さんであった。打ち込みは数千項目に及ぶ。あの忙しい業務の間を縫って、大変な作業量を任せてしまい、誠に申し訳ないことであった。実は、誰が入力作業をするのか何も決めていなかった。後になって、皆そのことに気が付いたのである。孫福さんは、創設時の面倒な作業を黙々とこなし、設立総会の準備作業の陣頭指揮をされたのであった。
設立総会が終わり、私が事務局長になることが決まった時、「はい、これ。後はよろしく」と渡されたフロッピーディスクには、それまでのすべての会員情報が網羅されていた。アッ、と思った。さすがだ。かなわないな。男は黙ってなすべきことをする、の気概が伝わる。
学会事務所事始め―丸善に感謝
事務局の仕事でもっとも大切なことは会員情報管理である。うれしいことに次から次へと入会の申請があり、入力ミスは許されないから慣れぬパソコンを前に緊張した。今だったらメールで迅速に連絡が取れるが、インターネットはまだ普及していなかった。それで、月に1回をめどに「事務局便り」を出すことにした。
B5用紙を半分に折った4ページ建てで、特に新入会員情報を周知することに留意した。会員になったものの、何の連絡もないということでは、会員相互の広がりも望めないし、仲間意識を得ることができない。1万円という会費は、決して安くなかったからである。
当時、亜細亜大学の総務部長をしていたので、印刷は印刷室の担当者に、封入・発送は私が部長をしていた女子バレーボール部の部員にお願いした。事務局長としては、事務所は大学内にあるほうが融通が利いて便利ではあったが、いつまでもこのままというわけにもいかない。けじめはつけなければとの思いもあった。
やがて会長の孫福弘さん、副会長の村上義紀さんの尽力で、丸善が日本橋本店5階の一室、20平方メートルほどの事務所を貸してくれることになった。表側は書店・文具等の名店である。学会事務所は裏側の社員通用口から入るのだが、丸善側の対応はまことに丁寧で快適だった。東京駅からも5分という一等地である。そもそもできたばかりの学会が事務所を構えられるような場所ではない。丸善としても、新しくできた大学行政管理学会を支援しようということである。学会としては、忘れてはならない草創期の歴史の一コマである。
会員のたまり場ができて学会の活動拠点が得られ、とてもありがたかった。何よりも独立した学会事務所が都心にできたことによって、社会的にも認知されたようで誇らしかった。しかし、せっかく事務所ができたのに、事務担当者がいなくては意味がない。たまたま、結婚して会社を辞めたばかりの娘に週に3日ほど手伝ってもらうことにした。
このころになると、業務処理も順調に処理されるようになり、学会の基礎もできてきた。
学会とJAFSAのこと
孫福さんや村上さんといつ、どこで知り合ったのか記憶にないが、1968年に発足したJAFSA(外国人留学生問題研究会、現・国際教育交流協議会)の活動を通じて知り合ったことだけは確かである。お互いに同世代という親しみもあった。私立大学連盟の活動も一緒だった。
大学行政管理学会の世話人、発起人にJAFSAの活動経験者が多いのは、大学横断的な職員の人的ネットワークが早くからあったことと無縁ではないだろう。日本の大学職員の歴史を語る場合、このJAFSAの存在は非常に大きかったのではないかと、私は考えている。
JAFSAがユニークであったのは、第一に国立、公立、私立という設置者の垣根を取り払った大学横断的な組織であったこと。第二にメンバーが大学職員中心であったこと、第三に国際交流という戦後の日本の大学にとって全く経験のない新しい領域を対象とした組織であったことにある。1967年に文部省は各大学の「留学生担当者研修会」を開いており、1968年にはJAFSAが発足した歴史を見れば、当初から国際交流関係の要員養成に文部省がかかわり、大学横断的であったことの影響がよくわかる。
事実、1960年代後半に入り、日本の大学にも外国人留学生が来るようになり、それに伴って大学の国際化問題が意識され始めたという時代背景があった。留学生を受け入れるということは、入試・広報から宿舎、教学、学生の厚生補導、外国教育事情、出入国管理業務等がひとまとまりの業務として連動し、外国語能力も必要とした。既存の部署だけで処理するにはやや面倒な業務でもあった。しかしこのことが、既存の組織や思考に風穴を開ける役割をはたした。
私は、1967年に中途採用で大学職員になった。増加しつつあった留学生への対応要員ということであった。たまたま亜細亜大学と香港中文大学新亜書院の第6期交換留学生として1963年から65年までの2年間を香港で学んだ経験があり、恩師に大学に戻って手伝えと言われたためであった。
学会で人生を豊かにしよう
学会は、言うまでもなく大学横断的な組織である。つまり個々の会員にとっては、単発的な研修会と違った、関心領域を共にする学外の仲間との継続的な交流の場を得ることと同義である。つまり、自大学以外に全国各地の大学に自分の先輩・同輩、後輩を持つことができるということでもある。
例えば、JAFSA事務局長で早稲田大学の外事課長をされていた山代昌希氏は、私にとって大学職員としての先輩であり、自分もかくありたいと願う人生の目標となった方でもあった。早稲田にはこんなすごい人が職員にいるという現実が、私の大学職員としての生き方に大きな影響を与えた。学外組織に参加することのよさは、そこに集う人たちからあらたな知見や刺激を得て、人生を豊かにすることができることにある。さぁ、タコつぼを出よう。
大学行政管理学会に感謝、感激!
山﨑 その 氏
京都外国語大学 総合企画室次長
2016年9月、第20回定期総会で第9回の孫福賞をいただきました。2001年に入会した頃の自分からは想像もできないことです。受賞については「事務局だより」第105号に小文を掲載していただいたので、ここではJUAMと関わった15年間を振り返って、感謝とともに胸に溢れてきた想いのいくつかを述べさせていただきます。
JUAMに出会うまで
私にとって三番目の職場となった京都外国語大学でアルバイトを始めたのは1989年でした。18歳人口がピークを迎えようとしていた時期です。入試ともなればトイレの数が足りず、中庭やグラウンドに仮設トイレを設置するほどたくさんの受験生が集まり、大学は活気に溢れていました。一方、現在ほど仕事に追い立てられることもなかったので、大学の将来構想から食堂のメニューまで職員同志はもちろんのこと、教員や学生も一緒に語り合う機会がたくさんありました。「大学って、一日中放課後みたいで楽しいところだなぁ」と思っていました。
ところが、数年も経たないうちに物足りなさを感じるようになりました。毎日、毎年、同じことを繰り返し、小さなことも大きなこともワァワァと議論をするけれど、その場限りで肝心なことは結局、何も変わらない。だからでしょうか、目の前の仕事が辛いわけではなく、職場の人間関係がギクシャクしているわけでもないけれど、なんとなく毎日が退屈でした。これという特別のことがあったのではなく、日常の些細なやり取りの中で、次第に閉塞感を感じるようになっていたのだと思います。いつしか「大学の内状はこんなもの。これが普通」と思うようになっていました。JUAMに入会したのは、この頃でした。
自分の「普通」は「普通」じゃなかった
JUAMに来ると、職場とはまったく違うタイプの人たちがたくさんいらっしゃいました。とくに私が初めて理事になった2005年当時の福島一政会長(当時、日本福祉大学)、近畿地区理事・監事の五十川進さん(当時、立命館大学)、河口浩さん(甲南大学)、五藤勝三さん(関西大学)、澤谷敏行さん(当時、関西学院大学)、津守浄子さん(当時、龍谷大学)、吉田由紀雄さん(同志社大学)、塩川雅美さん(当時、谷岡学園)は、皆さん個性的で、どこからパワーが出てくるのか不思議なぐらい情熱的でした。この方々と出会えていなかったら、大学職員の魅力に気づかず早々に辞めていたかもしれません。大学で働くことの意義や目的、その背景にある考え方、さらには一人前の職員がとるべき分別のある行動など、いろいろなことを何気ない雑談の中で教えていただきました。
五藤さんから西日本事務局を引き継がせていただいたのも、とても有難いことでした。近畿地区だけではなく中部や中・四国、九州・沖縄地区の理事の方々、学会事務局を担当されていた高橋清隆さん(東洋大学)、藤原喜仁さん(東洋大学)、そして誰を置いても市ヶ谷オフィスの坂本智子さんに出会うことができました。気風の良い坂本さんに助けていただいたことがたくさんありました。
任期中最後の理事会は2011年3月11日、東日本大震災の日でした。日本大学経済学部7号館で開催されていた第42回理事会は大きな揺れで中断。13階から階段で避難しました。すぐには何が起きたのかよくわからない状況でしたが、江端豊和さん(関西福祉科学大学)の的確な判断で、日大のすぐそばにあるホテルを予約することができました。余震の続く長い夜を、種田奈美枝さん(広島修道大学)、坂本さんと狭いシングルの一室で過ごしました。3人一緒で、どれほど心強かったかしれません。
昨今、AI(人工知能)が注目されていますが、コンピューターがどんなに発達しても、大学の仕事の中心が人間であることは変わらないでしょう。人と人との間に生まれる「縁」や「情」をこれからも大切にしていきたいと思います。
大学職員研究グループ
もうひとつ、JUAMで日常から少しかけ離れた違和感のある空間に出会いました。1999年に発足された大学職員研究グループです。JUAMのホームページにアップされている「大学職員―その属性」は、あらゆる大学職員に通底する課題が取り上げられています。その内容は緻密に論理展開されていますが、いわゆる「正論」だけではなく独創性に溢れていると感じました。発表当時から16年経った現在でも、大学のマネジメントを考える際の視座を示してくれる貴重なレポートだと思います。
私は2006年ぐらいからボチボチ参加していたように思います。合宿研修では、代表の各務正さん(当時、順天堂大学)や参加者から投げかけられる、単純だけれど答えのない問いに夜を徹して向き合い、浅い思考を繰り返す日常とは違う時間を過ごすことができました。
ひとつのことをやり遂げた瞬間は、もうこれで十分だと思いますが、しばらくするとまだ足りない、もっと良い方法があるかもしれないと考え出します。失敗した時は、もう二度とやりたくないと思いますが、しばらくするとまたチャレンジしたくなります。その時々の浅い思考で行動を繰り返すだけでは、経験を学びに変えることはできないと思います。深い思考の機会を、もっと多くの方に利用していただきたいと思います。
JUAMは失敗と成功を分かち合う場
SD(Staff Development)が2017年から義務化されることとなりました。大学(組織)の立場からすれば法令で縛られるまでもなく、経営資源である職員の能力を引き上げ、組織能力を高めることは経営戦略の一環として取り組む重要なテーマです。一方で、個人の立場からみた場合のSDは、誰かから何かを与えてもらうのではなく「お前が(O) 自分で(J) トレーニング(T)」、もしくは「お前が(O) 自分で(J)探究する(T)」という「OJT」が基本の考え方だと思っています。
私はJUAMの研究集会や研究会を、自主トレーニングの進み具合を客観的に確認できる貴重な場として思う存分活用させていただきました。失敗や成功の経験、研究によって得た私的な知見は、発表することによって異なる視点の質問や意見と交わることができます。そこで生じた反応が新たな知見となって共有され、この繰り返しの中から大学を支え動かす仕事が創り出されていくと期待しています。これまで鍛え、育てていただいた感謝の気持ちを形にして、JUAMのさらなる発展と何かしら社会の役に立つことに尽力していきたいと思います。
対談
水野 雄二 氏(獨協大学 教育研究支援センター次長)
足立 寛 氏(立教大学総長室渉外課担当課長 教育懇談会事務局/立教セカンドステージ大学事務室)
| 足立: | 今回の対談に当たり、水野さんにお聞きしたいのは、職員と、そしてそこに密接につながってくる大学行政管理学会(以下JUAM)の過去・現在・未来についてです。まずは長い間大学職員として大学改革を見つめてこられ、また第一線でも大学改革に携わってこられた水野さんの経験談からお話を伺いたいと思います。 |
| 水野: | 入職当時は、自分が担当する仕事の根拠を求めたいと思い、『大学関係事務提要』(ぎょうせい)と『大学運営の法律問題と基礎知識』(大学法令研究会編)を傍らに置き、大学事務について常に考えていました。入校当初は教務事務を担当していたので、例えば、単位の時間計算はどこから来ているのかということから卒業期日の時期はいつかという問題まで、あらゆることの根拠を求めることに興味をもちました。ある時ふと、これは事務の専門性は深められるが、事務仕事から脱却ができないのではないかと思いました。また、事務の専門性を超えていかないと、今で言う、教職協働はできないという思いに至りました。この時が1980年代でしたが、当時は教学事務というのは教員の補助的な仕事が多く、教学の周辺業務、また学生とは支援というより指導という立場で接していて、教務事務職員は教学マネジメントに十分コミットできていなかった時代のような気がします。私は殻を破り、事務職員からワンステップ上がることを考えると何らかの専門性を身につけなければならないと思っていました。 大学設置基準の大綱化(以下、「大綱化」)前において、自分の立ち位置を考えると、「大学は誰のものなのか」ということを念頭に置いて考えていかないとだめだと思っていました。具体的には「大学を必要とする人たちのため」と「大学が必要とする人たちのため」にという捉え方です。こういう見方をすると大学の大きな改革の流れや社会の流れが見えてきて、大綱化より遥か以前の1960年代から70年代の時代に起こった第1次ベビーブームやその後の大学紛争、大学臨時措置法、四六答申などがどういう意味を持つのかということが見えてきます。私自身そのように物事を見られるように努力をしてきたつもりです。 特に、1991年の大綱化は、今まで大学の「運営」は定型的に考えていけばよかったものが、定型を外され、後は自分たちで考えていかなければならないというスタンスに変わったところから、大学は「運営」から「経営」に自ずと変化し、大学自身の責任になったという大きな転換を迎えました。特に、教学の部分、アカデミックアドミニストレーションの部分については、大学が総力をあげて物事を考えていかなければならない、そこには大学職員も加わっていくという大きな転換であったと思います。それまでは18歳人口の減少についても話題になっていましたが、1992年の第2次ベビーブームのピーク以降18歳人口の急減等、大学を取り巻く環境が厳しくなっていくなか、自分たち自身がどのようなレベルアップをしなければならないかを模索して悶々としていた時代です。 その時に、大学行政管理職を考える大学行政管理学会という団体が登場しました。待ち望まれ、期待が大きく具現化された、大学職員にとって大きな転換の時代だったと思います。 |

| 足立: | そのような転換期の時代に水野さんも事務仕事から脱却して事務の専門性を超えて行こうと努力されたわけですね。具体的にはどのようなことから始められたのでしょうか? |
| 水野: | 当時、学内的にはこういう風に物事を見ることが多くはなかったのですが、細々ながらも少数の仲間が集まり、勉強会から出発しました。また、学外では、私立大学連盟の取組みや研修を通じて、孫福さんや村上さんと出会い、自分よりも先に考えを進めている人たちがいるということが分かり、嬉しかったです。1983年に読売新聞で、アメリカの大学職員について書かれた記事で大学アドミニストレーターという存在を知り、これを調べていたら、1984年に村上さんが『日本に大学アドミニストレイタは必要か』という論文を書かれていました。これは驚きでもあり、先行して研究活動されていた先輩がいたということは本当に嬉しかったことを覚えています。 |
| 足立: | 私も桜美林大学の大学院(国際学研究科大学アドミニストレーション専攻、現在は大学アドミニストレーション研究科)の一期生で、思いを同じくする人が初めて集まり、悩みを打ち明けられ、居心地がとてもよかったです。なかでも故・孫福弘先生の授業は各大学の寄付行為を持ち寄って違いを語り合うなど、毎回とても刺激的でした。ただ、当時はまだ私は大学職員ではありませんでしたが、学んだ成果を自分の大学に持ち帰って改革にいかにつなげるかというところで、なかなか賛同してくれる、あるいは理解をしてくれる職員がいないという現実もあると聞きました。職場が理解してくれず、隠れて通っていたという人もいました。教職協働も重要ですが、職職協働の必要性、つまりセクショナリズムではなく大学全体の中で職員間でも考えて行動していくことが必要だと思うのですが、実際には現実は解消されず悶々となってしまう。こういったことはJUAMの中で解消されていくでしょうか。 |

| 水野: | 思いを同じくする人が集まったところからそれを自分の大学に持ち帰っても理解され難いとのことですが、私の考えはその逆で、自分が抱える課題解決のために参加することを大切にしてきました。 また、自分のことを振り返ってみると、30年以上よくこのモチベーションが続いたと思います。なぜ続いたのかを考えた時に大学又は職場環境が好きだとか、生活の糧、いわゆる対価をよりよくするための動機だけでは続かなかったと思います。大学に対してもっと知りたいという好奇心こそが続けてこられた理由ではないかと思います。自分の好奇心から出ているので学ぶことは苦にはならないですし、単位の実質化への対応など、厳しい現実の中で、大学に対しての好奇心から得た様々な成果を学生に返すことができるという喜びと充実感もあるのだと思います。学内で仲間づくりをすることも大切なことですが、例えば10人いたら10人全員が同じ方向に向いてもらうよりも、1人でも2人でも、私がやっている仕事を見てもらうことで、共感してもらえればと思います。無理をして仲間づくりをしたことはありませんし、それは長続きしません。 |
| 足立: | JUAMに出会ったいきさつや、その後の関わりなどについても、お話しいただけますか。 |
| 水野: | 私がJUAMの運営と直接関わったのは、大学人事研究グループが設立された1999年4月からです。初代リーダーの原邦夫さん(当時、慶応義塾大学)と吉田信正さん(当時、法政大学)から、次のリーダーの依頼があり、お引き受けしたことから積極的にJUAMに関わり始めました。その後、JUAMの事務局長をやって欲しいとお話しがあり、お引き受けしたのですが、ちょうど同じタイミングで私大連盟の海外研修の副委員長もお引き受けしていたので、パンクしかけるほど忙しい時代でした。 JUAMの大きな転機としては、井原徹会長(当時、早稲田大学)の時に、JUAM会員の管理監督職を撤廃し、誰に対してもJUAM会員への道を拓きました。さらに、会員の地区の活動を2支部8地区制に仕切り直し、東日本支部と西日本支部に分け、副会長をそれぞれに置き、その下に4つずつ地区をつくり、また会計も分離しました。研究活動を執行部に任せるのではなく、各地区ができるだけ自主的に研究活動をできるようにしました。また、特別研究助成の補助制度も作り、研究活動の幅を広げられるようにしました。広く門戸を広げることで様々な人が入ってきて、いろいろな知識・体験が集まってきました。この学会が管理監督者のみであれば20年間維持するのは困難だったかもしれません。 |
| 足立: | 私はJUAMの立ち上げのときは大学と関わりのある民間企業に勤めていましたが、当時、管理職の職員のみが対象と聞いてなんと閉鎖的な学会だろうと思いました。しかし、その後20年経って振り返ってみると、徐々に会員の対象を広げていったこのやり方は実に正しかったと感じています。最初から若手職員や民間団体等のあらゆる層が入っていたら、カオス状態となり、さまざま要望が噴出して方向性すら決められなかったのではないでしょうか。創設メンバーの方々は、そのような状況に陥ってしまうのを危惧して、まずはマネジメント層に限定してスタートしたのでしょう。一方で、そういう風に対象を広げて1,400人近い規模になり、若手も入ってくるなか、これからJUAMはどういう方向に向かうべきなのか。この点の課題はどう思っているかをお伺いしたいです。 |

| 水野: | 今のJUAMに対する私の見方ですが、JUAMの「大学行政管理学会開設趣旨の説明と参加の呼びかけ」にも書かれているように、「プロフェッショナルとしての大学行政管理職の確立」について、それが本当に、最終的な目的なのか、あるいは手段なのかと考えたとき、私の理解では手段だと思います。その根拠として、学会規約第2条には「本会は、大学の行政管理について実践的、理論的に研究し、大学行政管理にたずさわる人材の育成をとおして、大学の発展に寄与する」と書かれています。これは自分自身が大学行政管理職になるだけでなく、なったことにより大学の発展に寄与してほしいというところがファウンダーの方々の最終目的だと思います。ここの「大学」とは大学全般、社会の中の大学に貢献して欲しいという意図ではないかと理解しています。そこから振り返り、今のJUAMを見ると、役員から中間管理職、若手などいろいろな方々が入ってきて、自分たちがそれぞれの思いでいろいろな活動をやっている。このような組織は比較的緩やかであってよいのですが、どこを目指したいのか、何をしたいのかが見失いがちになります。一方、執行部が強制的にこうやるべきというやり方は、少なくともアカデミックな環境を提供している学会に沿うものでしょうか。 もうひとつは、1,400人の会員数の存在があげられますが、日本全国の大学専任職員総数の2%に満たず、98%は未加入です。わずか2%に満たない人たちが集まっているこの学会をどう評価すべきなのかをきちんと分析する必要があるのではないでしょうか。毎年、事業計画で「JUAMの会員を増やす、女性会員を増やす」と掲げていますが、本当にそれが必要なのか。これは批判ではなく、振り返って考えたときにどうなのかということです。会員数を増やしていけば職能団体としては力強いでしょうが、学術団体から見れば会員数の多寡は重要な問題ではありません。事業計画として増やすということがどんな必要性があるのかをもっと議論しなければなりません。この議論をすることによって、職能団体か、学術団体かというところも自ずと見えてくると思うのです。私は職能団体か学術団体かという2元論で語らず、もっと自由な発想でJUAMを考えて欲しいと思います。 |
| 足立: | 確かにJUAMの会員がマネジメントクラスからスタートしたということで方向性はぶれず、今のJUAMの基の形ができたという面では良かったのですが、若手職員にとっては、そのことが返って「敷居が高い」と感じる阻害要因になってしまい、そのような低い比率に留まっているのかもしれませんね。また、学会規約に「大学の発展に寄与する」と書かれたなかでそこでの「大学」とは一体何を指すのかといった時に、若手職員にとってみれば自分の所属大学のことで精一杯で、そこを超えたところでの大学の発展ということについては想像がつかないのではないでしょうか。若手の人たちの勉強会では、お互いに仕事に関わる話を共有し、改善策を築いたものを自分の大学に活かすことを目指しており、それはJUAMが果たしている大きな役割の一つでもあるかと。だからこそ職能団体としての役割は大変大きいと思います。それを除いてしまうと若手は見向きもしなくなってしまうでしょう。だけど、学術団体としての学会とのバランスをどうとるのかということも必要であり、非常に難しい。これからの重要な方向性として、なんらかの学会像を示さないといけないんじゃないかと思うのですが、どうでしょうか。 |
| 水野: | 少なくとも大学という職場で大学職員としての成長を望むのであれば、20代でやるべきこと、30代でやるべきこと、40代でやるべきことがある。これに自分自身のライフサイクルを重ね、少し長いスパンで物事を見てもよいのではないかと思います。足立さんがおっしゃるように、20代の学会の会員の方々は、高等教育行政のゆくえや所属大学の経営状況よりも、もっと現実的な課題として、自分の職場について、自分の課の仕事の質を向上させたい、職場の人間関係をより良くしたい等の課題を抱えていると思います。それはそれでよいのです。30代になったときに、役付きになって仕事が見えた時に、もう少し違う景色が見えてくるものがあるはずです。その違って見える風景を把握し、次の風景を見据えるために長いスパンの「学び」が必要になる訳です。要は、自分が大学職員としてあるいは社会人としてどのように成長したいのか、どんなキャリアを積んでいきたいのかというところを見据えていかなければならない。JUAM設立当初から、研究・研修委員会を置いた意味はそこにあると思います。20代、30代の人たちが、そういったところで育つあるいは育てられる契機として。しかも職場や大学という場を超えたところで自律的に育っていく環境に飛び込めるものを作って、それを育てる。そして、それ以上のところは自分自身で成長してくださいね、という意味で研究・研修委員会が置かれている。学会規約第2条にある人材育成のとおりです。そういう方々が30、40、50代になり、大学経営に関わった時に、身につけた知見に基づいて、自分の所属課や部、さらに所属大学を超えて、もっと高いところから物事を俯瞰して見られるような人材に育って欲しい。そこにJUAMとしての大学アドミニストレーター養成の意義があると思います。 もう一つ付け加えるのであれば、大学アドミニストレーターは、その所属大学だけで通用する人材ではないと考えます。所属大学が替わっても大学アドミニストレーターとして活躍できなければならない。だからこそのプロフェッショナル人材なのです。自分の所属大学を超えた大学アドミニストレーターへの成長こそ、JUAMは求めています。 |
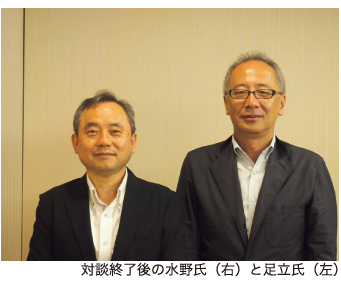
(記録・撮影:染川 真由美)
澤谷 敏行 氏(大学行政管理学会 名誉会員)
五藤 勝三 氏(学校法人関西大学 常務理事、法人本部長)
河口 浩 氏(甲南大学 学長室事務部長)
大学職員を志したきっかけ
| 澤谷: | 1973年に関西学院に入職しましたが、高校教員を目指していたんです。当時、高校教員は人気で採用試験に落ちましてね。それで3月23日にあった採用試験を受けたんです。3回目くらいの募集だったのかな。面接ではぼろくそに言われて “これはあかん!”と思ったけど、翌日に健康診断を受けてくれと連絡があって、受けたら4月2日から来てくれと言われました。思ってもみない採用でしたが、配属が図書館ということだったので、それなら勉強できるかなと思って、高校教員になるための準備期間のような気持ちで大学職員になりました。 |
| 五藤: | 大学3年生の時に、立命館の元総長の末川博先生著の『彼の歩んだ道』という本を、本屋で見つけました。その中に「人生3分論」というのがあって、「人は25歳くらいまでは人に育てられたり、支えられたり、教えられたりして大きくなっていく。25年を過ぎると今度は社会のために貢献する。50歳になると悠々自適に自分の人生を歩めばよい」というようなことが書いてあったんです。これを読んで“なるほどな、人の役に立てたらいいな”と思いました。第1希望だった公務員には募集がありませんでした。そんな時、たまたま就職課に行ったら、今年は採用があると言われ、11月2日に試験を受け5日に内定の連絡をいただきました。その時は、“大学に就職して、自分が思い描いていた「人の役に立つ仕事」ができたら”という気持ちがありました。 |
| 河口: | 大学職員を目指していたわけではありませんでしたが、私の姉が卒業した短大の職員で、楽しそうにいろんな仕事をしていて、大学はやりがいのある職場なんだなと思っていました。それで、入学試験を受験した時の印象がよかった甲南大学の求人票が、母校の関西大学に来ているのを見つけて、採用試験を受けましたが補欠という連絡がありました。すでに内定をもらった団体に行くつもりでしたが、12月になって甲南大学からこないかという連絡がありました。迷いましたが姉の話もあったので、大学は学生が社会に出ていくのを支える仕事なのでやりがいがあるだろうと思ったのが、入ったきっかけでした。 |

| 澤谷: | 当時は、あまり大学事務職員という職業は確立していなったですね。どんな仕事をするのかというのが分からなかった。 |
| 河口: | 採用面接では「大学職員ってどんな仕事をすると思う?」と聞かれたことが一番印象に残っています。“来たか!”という感じでした。 90年代になってからですかね。大学職員の人気が出てきたのは。 |
| 澤谷: | 当時は給料が低くて、僕が入った時は4万円くらい。家賃を払ったらあと3万円しか残らなかった。 |
| 五藤: | あの時は2・3年したら給与が全然ちがっていましたね。僕の時は12万900円でした。 |
| 澤谷: | 職場の秋闘で3月に給与が決まって、4月にさかのぼってかなりの差額が支給されていましたね。 |
JUAM入会まで
| 澤谷: | 入職したころは、それぞれの上司が思い思いに職員像の絵を描いていました。当時は、自由に絵を書いてよかったんです。僕はと言うと、夏休みがあるから、旅行に行ったり山に登ったりしていました。大学紛争の頃だったので、1年間に7・8回バリケードを外しにいったこともあります。 |
| 五藤: | 入職してから、大学行政管理学会ができるまでの間に大学職員の仕事はだいぶ変わっていきましたね。僕が就職したころは、親や親せきから必ず「上の人の言うことを良く聞きなさい」と言われた。大学に入っても、先生の言うことを良く聞きなさいという時代でした。入職以来、人事担当の経験が長く、研修や人事制度に関心があり、いろいろ勉強しました。当時、人事院主催の事務系第一線リーダー(係長等)を対象としたマネジメント研修(JST:Jinjiin Supervisory Training)の指導者養成コースに参加すべく2週間ほど東京に出張しました。その時に、某損保会社の課長さんから、「大学っていいよね。我々みたいに競争がないし、黙っていても学生が入ってくるし、楽でいいよね」と言われたんです。それを一日目の夜の懇親会の時に言われて、カチンときました。次の日、朝のプログラムの中で、参加者の業務内容を説明する機会があり、大学職員の仕事について熱弁を奮いました。その日の夜も懇親会に誘われて行ったところ、昨日の課長さんから、「五藤さん、昨日は失礼なことを言って申し訳なかった。大学も企業も大変なのは同じなんだね」と言ってもらいました。その当時は、今ほど大学事務職員の仕事を理解している人がいなかった時代だったので、なめられたらあかんというか、私としては大学事務職員の仕事をアピールしておきたいという気持ちがあったんでしょうね。 |
| 澤谷: | 企業というのは目標がはっきりしていて、それはそれで大変だと思いますが、大学の難しいところはそれぞれが自分で目標を作らないといけないところですね。 |
| 五藤: | とは言え、私自身も当時は“大学の仕事はぬるいな”ということはそれとなく感じていました。だから、意識的に人事制度や研修制度等で企業がやっていることを研究して、そこから学ぶべきものを取り入れて研修制度や人事制度を運営していました。たしかに、澤谷さんがおっしゃるように、自分で目標を立てていかないとやっていけない、そんな時代だったかもしれないですね。 |
| 河口: | 入職時は、職員組合全盛期で、大学では学生サービスや学生の権利というより、労働者としての権利が主張されていました。思っていたのと違うなと、カルチャーショックでした。配属されたのは会計課でしたが、職員をなんとかしなければいけないという思いがあり、人事関係に行きたいと思っていたところ、経済学部事務室を挟んで総務部人事課に行くことができました。 |
JUAMとの出会い
| 澤谷: | 図書館、法学部、学長室を経て、国際センターに配属になりました。国際関係の仕事は、どこの大学も80年代に立ち上げ、結構全国ネットで活動をしていました。私大連盟で国際関係の研修会があって、そこで孫福さん(当時、慶応義塾大学)や山本さん(同、亜細亜大学)、宗像さん(同、青山学院大学)と出会いました。それと現在と正式名称は違いますがJAFSA(当時、外国人留学生問題研究会。現、国際教育交流協議会)という組織があって、そこでもいろんな人と出会っていました。その人たちが、専門職では大学を変えられないと考えるようになったんです。孫福さんもその中の1人で、その人たちが大学行政管理学会を立ち上げたという情報が伝わってきました。立命館大学の阿曽沼さんや関西大学の小西さんから、我々も入ろうということで連絡があり、設立時からの会員になりました。当時は管理職しか入れず、当初の会員数は約350人でした。すると、入ったとたんに研究集会で発表しろということになったんです。1997年9月に法政大学で開催された第1回の研究集会で、僕が発表させてもらって、その後で孫福さんが発表されました。その時発表した内容を論稿にして学会誌第1号に掲載してもらいました。それがこれです。 |
| 五藤: | 僕は1977年に職員になっています。ちょうど20年、人事課で課長補佐の時だったと思います。設立2年目の1998年に入会しました。自分の関心のあるテーマの勉強ができることや大学間のネットワークができることに期待しました。学会の設立によって、大学職員には専門性が必要というムードが一層高まってきていたと思います。仕事との両立は大変でしたが、いろんな人の話を聴けて勉強をさせてもらいました。 |
| 河口: | 私の場合は、学会に入会している大学の先輩から入らないかというお話はいただいていましたが、私なんかまだまだという思いがあり躊躇していました。2002年2月に入会しましたが、入会した後もしばらくは幽霊会員で、総会や研究集会、研究会に参加したことはなく、送られてくる学会誌を見て参考にする程度で、レベルの低い会員だったと思います。 |
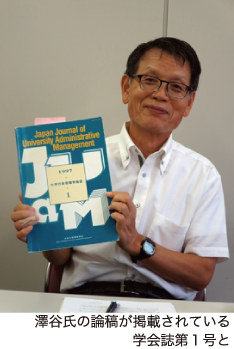
| 五藤: | 僕は1977年に職員になっています。ちょうど20年、人事課で課長補佐の時だったと思います。設立2年目の1998年に入会しました。自分の関心のあるテーマの勉強ができることや大学間のネットワークができることに期待しました。学会の設立によって、大学職員には専門性が必要というムードが一層高まってきていたと思います。仕事との両立は大変でしたが、いろんな人の話を聴けて勉強をさせてもらいました。 |
| 河口: | 私の場合は、学会に入会している大学の先輩から入らないかというお話はいただいていましたが、私なんかまだまだという思いがあり躊躇していました。2002年2月に入会しましたが、入会した後もしばらくは幽霊会員で、総会や研究集会、研究会に参加したことはなく、送られてくる学会誌を見て参考にする程度で、レベルの低い会員だったと思います。 |
『大学職員のための人材育成のヒント』の出版
| 澤谷: | 2005年にJUAMの副会長を拝任したんです。西日本の支部長を兼ねて、西日本の活動を方向づけないといけないということで、いろんな分野に活動を広げたりハイキングを企画したりしていました。我々3人はその頃から一緒にやってきました。関係が密になるきっかけは、「失敗事例から学ぶ人材育成」です。親しくなって、話をしているうちに、職場の愚痴を話すこともあったんです。これは他の職場でもあることではないかということで、「事例を集めてまとめたらどうや」という話になりました。最初に研究集会で発表したのは2006年9月の青山学院大学でした。 |
| 河口: | 私が澤谷さんと初めて会ったのは2005年の札幌大会でした。五藤さんには、それ以前からお世話になっていました。総務部にいる時に7私大の労務問題懇談会というのがあって、その頃から関西大学の五藤さんは有名でいろいろご指導いただいていました。2005年の札幌大会の時に五藤さんに一緒に勉強しようと誘われたんです。 |
| 澤谷: | 2006年9月に発表するため、夏に千刈にある関学のキャンプ場で合宿しました。西日本の理事にも事例を募集し、いくつか出してもらいました。 |
| 五藤: | おかしいというご批評をいただいたり、好評をいただいたりしました。 |
| 澤谷: | 発表のセッションに参加した人からは面白いという感想でした。 |
| 五藤: | その当時の大阪府の企画室長が『企画室あれこれ』という小冊子を作っておられて、よく新人研修で使わせてもらっていたんですが、挨拶や報告の仕方、職場の人とのつきあい方などビジネスの基本になる事例を、20か30ほど集めておられ、関西弁丸出しで面白おかしく書かれているんですが、ものすごく参考になった。ちょうど、3人で打ち合わせをした後、晩ご飯を一緒に食べに行って話をしている時に、本を出そうかという話になりました。教科書を書いてもしかたないので、失敗事例をまとめてみるのはどうかという話になったんです。僕の中には、この『企画室あれこれ』がイメージとしてありました。 |
| 澤谷: | 2006年に発表した後、2年後くらいにもう一度研究集会で事例研究をやりました。その時も参加した人からは大変好評で、もっと読みたいということで、関学出版会に話をしたら、「こんな本を出版しても良いのですか?」と言われた。大丈夫ということを伝えたら、「出版しましょう」ということになりました。1,000部印刷しましたが、1か月か2か月くらいで、すぐになくなって増刷することになりました。 |
| 五藤: | 企業の人からは、「なんで“大学職員のための・・・”という書き方をするのか。企業でも当てはまる事例なのに」と言っていただきました。1か月くらいたったら900円に戻りましたが、出版間もない頃、アマゾンで2,400円位までいったことがありました。 |
| 澤谷: | ジュンク堂か紀伊国屋の教育関係で、その週のトップの売り上げになったこともありましたね。 |

第2弾出版に向けて
| 澤谷: | 大学基準協会の『大学職員論叢』の書評の中に、若手職員の人材育成も考えてほしいと書かれていたので、そういうニーズがあるのであれば、もう少し研究を続けてはどうかと3人で話し合っています。前回は管理職の悩みを解決する事例を取り上げたので、次回は若手の悩みに沿った事例を取り上げて、職員の人材育成の理論的解明につながるようなことができればと考えています。 |
| 五藤: | 若手職員からも「一緒にやらせもらえませんか」という話がありました。 |
| 澤谷: | 若手の悩みは我々にはわからないので、若手にも加わってもらう必要があります。今の若手職員が将来のキャリアプランについて不安を持っているのではないかと予測はしていますが、そういうもので具体的な事例が出てくれば、考えていく材料につながるのではないかと思います。直接的にこうだ、ああだと言うのではなく、事例を通じて学び取ってほしいと思います。 |
| 五藤: | ケース作成の要素として、組織の構成、システム・制度の問題、人間関係・メンタルヘルスの問題、そして、組織文化・風土の問題が入っていることが必要です。そうでないと、自分が悩んでいる問題をそのまま出してしまっても、研究用のケースにはなりません。 |
| 澤谷: | 出版できればよいですが、出版できなくても事例研究を若手職員と一緒にやって、自分たちの問題をはっきり捉えて、自分のキャリアプランを考えてもらえればよいと思っています。 |
| 五藤: | あえて答えを提示しない。それぞれで考えてもらいたい。組織風土等の違いにより、答えは異なります。ただ、様々な角度から条件等を考えて、解決策を考えることがすごく大事なんです。 |
| 澤谷: | 事例はあるが、解決策はそれぞれの大学でばらばらです。事例に対して、さまざまな考え方を出すことが役に立つと考えています。 |
| 河口: | 私の若いころと違って環境もかなり厳しくなっているので、そういう環境の中での悩みが出てくれば、面白いものができると思います。 |
| 澤谷: | 組織風土は設置形態の違い、規模、地方、都心、設立母体の違いなどで随分と違ってきます。そういうことを意識しながら、実際にはいろいろな考え方があるということを示します。その中から、読む人が自分にとってどういう答えがベターなのか、ワーストにならない答えなのかを読みとってもらえればよいのです。 |
| 五藤: | 第2弾を出版するかどうかの検討は、まだ始まったばかりです。 |
| 澤谷: | 今度の研究集会で発表をして、その反応を見て、それが面白いということであれば、若手職員の協力も得て、もうちょっと続けていきたいと思っています。 |
JUAMの活動で一番思い出に残っていること
| 澤谷: | 第3回孫福賞をもらったことです。日大で2008年の総会の後でしたが、自分のターニングポイントになったと思います。あと、理事から副会長をしていた時期に西日本の理事を中心に海外の視察を企画して、中国や韓国、台湾の大学を訪問したことです。楽しかったですね。 |
| 五藤: | 澤谷さんが支部長で、僕が西日本事務局長をやっている頃が思い出に残っています。当時、僕は人事課長をしていて仕事との両立は大変でしたが、当時の大学改革研究会へもっと多くの人にきてもらおうと、色んなことを企画しました。 |
| 澤谷: | 当時、教員評価で高知工科大学の坂本先生に連絡して来てもらった。 |
| 五藤: | あの時、すごく充実していましたね。西日本支部の事務局長という立場で、一番嫌いなお金の管理をしないといけないのは大変でした。もう一つは、やはり昨年の第19回総会・研究集会を関大で開催していただいたことですね。嬉しかった。たくさんの近隣の大学の皆さんに協力していただきましたし、私ども関大の職員も協力してくれました。初めて500人を超える参加者に集まっていただきました。 |
| 澤谷: | ボランティアのひとりでしたが、関西ならではの雰囲気がすごくありましたね。「笑い」についての講演も面白かった。五藤さんの人柄が大会運営全般にも醸し出されているようでした。 |
| 河口: | 私の場合、一番は本が出版できたということなんですけど、それ以外では、西日本に財務をテーマにする研究会がなかったので2010年に、当時、追手門学院にいらした垣尾さん(現、享栄学園理事長)、常翔学園の吉野さん、大手前大学の藤田さんにお願いして、財務問題研究会を立ち上げたことです。今年7年目にはいって、10月15日には20回目の研究会を予定しています。 |

大学職員だからできたこと
| 澤谷: | 教員ではなく、職員だったからできたこととして、新しい部署を立ち上げたことです。職員が作って安定してくると、そこに教員がやって来るパターンが多い。最初は職員が地固めするんですよ。それは職員にしかできないのではないかと思います。 |
| 五藤: | 人事の経験が長いので、現行の人事制度や研修制度の整備や再構築(リニューアル)等に関わらせてもらったこと、それと企業年金制度を創設したことです。それと学外の関係では、人事という狭い世界しか経験できない状態でしたが、その分、国家資格等をとることによって外部の人と関わろうと、特定社会保険労務士の資格を取りました。シニア産業カウンセラーや1級のキャリアコンサルタント、それに労働審判員をやらせてもらっています。企業の人がほとんどの中、大学に所属している人がいるということで、いろいろな経験をさせてもらうことができたのではないかと思います。 |
| 河口: | 本当は、学生と一緒に過ごして社会に送り出す喜びを味わいたかったんですが、配属された場所が会計課、経済学部事務室、総務部、財務部、現在は学長室で、学生サービスに直接かかわる部署は一度も行ったことがありません。職員と中高教員の人事・給与制度を担当してきたことと、財務部の時に、予算の学長裁量枠をぜひ作ってほしいと財務担当理事にお願いして、その後2年間「教育力の甲南」推進プロジェクト枠という予算枠を作って、次の財務部長にバトンタッチできたことが職員の立場でできたと思います。 |
大学行政管理学会の意義について
| 澤谷: | JUAMの意義は、実践と理論の往復運動にあると思います。実践をやってそれを理論化して、その理論をもう1回実践してみるという、そういうことができる場じゃないかと思います。もともとの発想は実践を理論化するということですが、実際には世の中がどんどん変わっていくので、理論化が追い付かないところがあります。でも、普遍性は見いだせなかったとしても、どこかである程度、理論化していく作業をしなければいろいろな経験が残っていかない。そういうのがJUAMの意義ではないかと思います。事例研究はまさにそれなんです。記録に残していくことで、いろんな大学の人たちの参考になっているのではないでしょうか。 |
| 五藤: | 我々は3人とも考えが一緒で、実務をやっていて、実践と理論をどういう風につないでいくのかということを考えながらやってきました。一方で、学会という名称にこだわって、もっと理論化しようという研究志向的な方もいて、それはそれで否定はできないと思いますが、大学事務職員の学会ということであれば、やはり実務を理論化するとか、実務と理論をどう結び付けるとか、そこはとても大事ではないかと思います。もっとも、いろんな考え方の方がおられてもいいと思いますが、そういうことを自分で勉強できる、そして、活動を通じていろんな方とネットワークが築けるというのが学会の最大の意義ではないかと思います。 |
| 河口: | 全国各地で様々なテーマの研究会が開催されていて、それを通じて能力開発ができたり、小規模の大学にとっては職員の人材育成に資する、そういう重要な役割を担っている組織・団体だと思っていますので、そういう面をもっともっと強くして行っていただけるとありがたいと思っています。 |
最後に、これからの大学職員に求められるものと大学職員への期待について
| 澤谷: | 大学職員に求められるものというと、毎年毎年増えていて、多すぎて大変だと思います。逆に、何の能力をつければよいのかわからない。文部科学省のグローバル人材の定義を見ていたら、すべてを満たすような人間はいない。いたらスーパーマン、いやスーパーマンはアメリカ人、日本人だからウルトラマン、それはちょっと無理だと思っていて、一つだけをあげることにするとゾンビのような人ですね。メンタルの面で強くなってほしいと思います。ゾンビというと表現が悪いが、マラソンをやっていると、途中で棄権したいと何度も思うのですが、周りに励まされ、少しするとまた走れるようになる。そんな感じですかね。失敗しても立ち直れるストレス耐性があり、自分で道を作っていくことができる人、「もがく力」が一つあればよいと思います。 |
| 五藤: | とはいえ、専門性を身につけていかないといけない。なにもかも身につけていくことはできないので、自分がいるポジションの中でどう掘り下げていくかという姿勢がないとだめだと思います。少なくとも自分がやっている仕事の内容や根拠を正しく理解しているとか、前例も把握しているとか、法的な根拠や大学全体の中での仕事の意義、これらが分かっている職員でなければならないと思います。社会人基礎力ということが言われますが、特に窓口に立っている人は、学生から見たら“あの職員が社会人基礎力のモデルだ”と思われる。それくらいの緊張感を持ってやらないと、高い学費をもらっていて申し訳ない。そのためには、どの部署にいても、自分の仕事の先に学生の姿がちゃんと確認できないと、大学職員をやってはだめかなという気がしています。人から見て人間的な魅力や安心感、安定感を感じてもらえるような職員になってほしいですね。 |
| 河口: | ITの強い人とか、英語の話せる人とかいるが、ITの知識はあっても自分たちの仕事の本来の目的を理解できないような人が出てきている。スペシャリストとしての能力も大事だが、それ以前に大学職員としてプロフェッショナルな仕事をするという意識をもっていないと、その人が将来、管理職になるときに困るんじゃないかと思います。 |
| 五藤: | 専門性というときに、上司や先輩がしっかり部下や後輩のそれを見極めてあげて、部下・後輩のキャリア形成を支援してあげることが、その職員の職業人生を豊かなものにすると思います。 |
| 澤谷: | 専門性と言うと若い人はスペシャリストの方を向いてしまいがちですが、それとゼネラリスト的な部分をつないで、プロフェッショナルな職員をどう育成していくか。つなぐことができないと、学校の目的とずれてしまうことを頭の中におく必要があります。 |
| 河口: | 自分自身はできなかったんですが、大学職員としてしっかりとした知識・能力を身につけて、大学運営をリードできる職員として育っていって欲しいですね。まだまだ教員に頼っているようなところがあるので、自分自身で大学を変えていく、作っていくという意欲を持った職員として成長していって欲しい。そのためには、自分が大学職員としてこのようになりたいというキャリアプランを持って日々過ごすよう心がけてもらいたいです。 |
| 澤谷: | 孫福さんは、専門職だけでは大学を変えることができないということに気がついて学会を作られたと思います。アドミニストレータは、教員からも職員からもなれるが、教員とか職員の枠組みの中では実現しません。「その枠を乗り越えた人間」でないとだめだということではないかと思います。日本でアドミニストレータは実現できていないように思うので、学会としては孫福さんの目標としていたものに向かって進んで行って欲しいと思います。 |
(記録・撮影:住 智明)
対談者
山咲 博昭 氏(関西大学)
松田 優一 氏(関西大学)
森川 一揮 氏(関西福祉科学大学)
コーディネーター
東芝 青児 氏(帝塚山大学)
JUAMへの入会のきっかけ
| 東芝: | さて、これから皆さんにはJUAMへの想いをテーマに対談いただきます。よろしくお願いいたします。 初めに、JUAMに参加しようと思われたきっかけをお聞かせください。 |
| 山咲: | 私は、内定後に学生として活動に関わっていたピア・サポートの合宿があったのですが、その際にご一緒した五藤法人本部長(学校法人関西大学法人本部長:元JUAM常務理事)からJUAMの存在をお伺いし、活動内容に興味を持ちましたので、入職後すぐに入会しました。 |
| 東芝: | 最初は大学行政管理学会と言われてもイメージできなかったのではないですか。 |
| 山咲: | 確かに最初は何をする学会なのかイメージできませんでしたが、五藤法人本部長から詳しいお話を伺っているうちに、大学職員が実践的な知識を学ぶ場であると知って入会しようと思いました。 |
| 松田: | 私は山咲から他大学の有志の若手職員が主催する勉強会があると誘われ、その勉強会に参加して多くのJUAM会員と知り合ったのがきっかけです。最初はこのような学会があって、私と同じような立場の大学職員が研究発表をしていることに驚きました。 |
| 東芝: | 確かに「研究発表=教員がするもの」というイメージがありますよね。 |
| 松田: | 発表の目的が少し先生方とは異なりますが、知識を共有するという意味では同じかもしれません。 |
| 森川: | 私も、本学の当時法人本部長だった上司に勧められて入会しました。大学としても、中堅職員や若手をJUAMに入会させる動きもあったと思います。勧められると断れない性格なので、なんとなく入会しました。 |
| 東芝: | 所属大学がJUAMに理解があったということですね。きっかけはどうであれ、JUAMに参加して初めて分かることも多いと思います。 |
| 森川: | 確かにそうです。JUAMに入会していなければ、ここにもいなかったと思います。 |
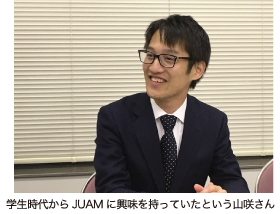
大学改革研究会(テーマ別研究会)を立ち上げた経緯
| 東芝: | 若手・中堅職員の研究会である大学改革研究会の三役を務められていますが、そもそもどうしてこのような研究会をはじめようと思われたのですか。 |
| 山咲: | 近畿地区研究会のハイキング(交流会企画)に参加した際に、近畿地区の理事の方々から「若手の勉強会をやってみないか」とお話をいただいたのが始まりでした。 |
| 松田: | そうそう、「若手で何かしてみなさい」ってね。 |
| 森川: | 私は「えっ?何を?」って思いましたけどね。 |
| 松田: | そして、2012年、当時、近畿地区研究会と一体的に運営されていた大学改革研究会を独立させ、私たちが引き継いだんです。元々は、澤谷さん(大学行政管理学会名誉会員)や大島さん(立命館大学)が実践的な知識をワークショップの中から学ぶ勉強会を作ろうと考えられて立ち上げられたと伺っています。 |
| 東芝: | 今も「ワークショップを中心に」という考え方は引き継がれていますね。 しかし、当初メンバーが3人だった時は、企画の準備など大変だったのではないですか。 |
| 森川: | かなりきつかったですね。企画前日に徹夜とかもしていました。 |
| 松田: | より良い企画を作ろうと情報収集や資料作成にもこだわりました。 心配性の私は、精神的にも肉体的にも辛かったのを覚えています。山咲や森川君との関係がギクシャクしたこともありました。 |
| 山咲: | 今となってはいい思い出ですね。 |
| 松田: | 準備の段取りなどは手探りでしたからね。今考えると、3人で深夜まで準備したあの日々が現在の大学改革研究会の礎だと思います。 |

学会活動で得たもの
| 東芝: | 皆さんはJUAMで活動されて5~6年ほどになると思いますが、その過程で得た知識や経験などをお教えください。 |
| 山咲: | やはり一番大きいものは、全国に亘る大学職員の方々とのネットワークでしょうか。特に共に活動する同世代の職員との繋がりは、研鑽を続けるモチベーションになっています。また、入職年数や役職などに関係なく、様々な方々からご意見やアドバイスをいただけることや、そこから新たな気づきや問題意識を得られたことも挙げられますね。 あと、大学改革研究会のワークショップを初めて関東で行った際もJUAMのネットワークに助けられました。2014年に東京に出向していた当時、関東では若手・中堅職員向けの研究会が開催されていなかったんです。そこで、関東でも研究会を開催しようと思ったんですが、会場を探すのも人を集めるのも知り合いが少なくて実現させるのは難しいなって思っていました。しかし、実際に開催する際には関東の会員の方に周知等にご協力いただき、結果として2014年度に2回の研究会を開催することができました。これは、全国的なネットワークを持つJUAMだからこそできる話かなって思いますね。 |
| 松田: | 確かにそうですね。私も他大学の方々との交流は、非常に貴重なものだと感じています。切磋琢磨できる仲間がいてくれるおかげで、多くの知識を得ることができました。 また、時宜に合わせたテーマ、自分達が求めるテーマについて他者から学ぶ中で、日常業務では気付かない、自分自身の未熟さを知ることもできました。今では、多くのメンバーが主体的に大学院等で研鑽を積み、研究会内外で発表を行うまでになりました。研究会という環境が私たちを成長させてくれていると思います。私も他大学の同年代の方々との繋がりは、大きな財産だと思います。 |
| 森川: | プライベートでも交流を深める程に仲の良い友人もたくさんできましたし、同じような境遇の人たちが頑張っているのかと思うと、「自分も頑張らなくちゃ」という気にさせられます。また、部署異動をした先で、以前学んだ知識が活かされることもあり、スムーズに業務を覚えることができたということもあります。 文科省のことなど、違った視点で物事を捉えたり、色々な情報にアンテナを張る癖も身に着きました。 |
| 山咲: | みんなが大学院などで研鑽を積むきっかけになったのは、外に出ることで所属大学の中だけでは得られない気づきや学びがあったことが大きいでしょうね。 それが自分達のキャリアを考える1つのきっかけになったと思います。 |

これからのJUAMに期待すること
| 東芝: | さて、JUAMは今年で20周年を迎えたわけですが、今後も皆さんは大学職員として研鑽を積んでいかれると思います。その中でこれからのJUAMに期待したいことはありますか。また、ご自身はJUAMにどのように係わっていきたいかをお聞かせください。 |
| 山咲: | せっかく大学職員中心に運営する学会ですので、その良さを今後ともしっかりと伸ばしていっていただきたいと思います。閉鎖的ではなく、多くの大学職員が参加できる場と言えばいいでしょうか。研究ばかりでなく、敷居が低く参加しやすい場であることが職員の作る学会として意味があることだと考えています。そのためにも、若手・中堅の職員が中心となって活動できるように、学会として仕組みを作っていかなければなりません。テーマに縛られず、プロジェクト型の世代横断的な研究会企画をしても面白いかもしれません。 |
| 松田: | 私もJUAMは今の長所を伸ばしていくのが良いと思います。学術研究団体なのか職能団体なのか分からないと言われる方もいらっしゃいますが、中間に位置する学会だからこその価値があると考えています。ずるい言い方かもしれませんが、会員次第でどちらの良いところも得られる場であることが、JUAMの良い点と思っています。 |
| 森川: | JUAMでの学びに限らず、学んだことがすぐ現場に繋ることは多くないかもしれません。でも、様々な知識を吸収することで、それらを総合して最終的に自分の業務やキャリアに繋がっていくと思います。 ですから、JUAMは気軽に学びを得られる場であってもいい。加えて、職員同士がネットワークを作る場であり続けて欲しいとも思います |

同世代や若手職員へのメッセージなど
| 東芝: | 最後に、全国の若手職員へのメッセージをお聞かせください。 |
| 山咲: | 若いうちは与えられた仕事をきっちりすることが必ず求められますし、それが当たり前です。そこに終始せず、自身で問題意識を持つためにも、視野を広くして自大学の問題に自身が中心となって取り組む姿勢が必要だと思います。 |
| 松田: | そうですね。現実や将来を悲観するだけではなく、今自分たちにできることはないかを考えたいですね。周囲が変わらないならば、まずは自身が変われば良いと思います。厳しい時代だからこそ、我々は、教員・職員という従来の枠を越えて「大学人」としての自覚を持たなくてはなりません。プロ野球の選手が自主的にトレーニングをするように、我々も自大学ひいては我が国の高等教育の発展に貢献できるよう、自主的にトレーニングをすることが必要だと思います。日々の実践だけでは活躍できるようになりません。環境への深い理解とトレーニングがあってこそ、チームの戦力となれると思います。知識に裏打ちされた実務を遂行できる「プロ大学人」を目指して、共に学びましょう! |
| 山咲: | 私も同じ意見です。結局のところ、能動的・主体的に学ぶことを学生に求めているのに、自分たちがしなければ説得力がありません。学生に「アクティブ・ラーニングを!」と言っているのであれば、自分たちもアクティブに学ばなければいけないと思います。それと、新しい取組みに批判的な方もいますが、まずは自らが一歩踏み出して行動することが大切だと思います。 |
| 森川: | 私はお二人のように高い意識をもって入会したわけではないですが、必ずしも高い目標を掲げる必要はなく、とりあえず、気軽に参加してもらってもいいと思っています。会員の方は近くの研究会にふらっと参加するのもいいですし、非会員の方はとりあえず入会してみたり、非会員でも参加できる企画に参加してみてはどうでしょうか。すぐに結果に結びつくことは少ないかもしれませんが、後々役立つこともありますし、何より楽しいです。やってみるかみないかは、結局は自分次第です。 |
| 東芝: | 「まずはやってみる。研鑽は自分次第!」ということですね。学会はアウトプットもインプットもできる場所であり、かつ失敗もできるので、自分の知識をどんどんブラッシュアップできる場であるというわけですね。今後も皆様のご活躍に期待しております。 本日はお忙しい中お集まりくださり、ありがとうございました。 |

